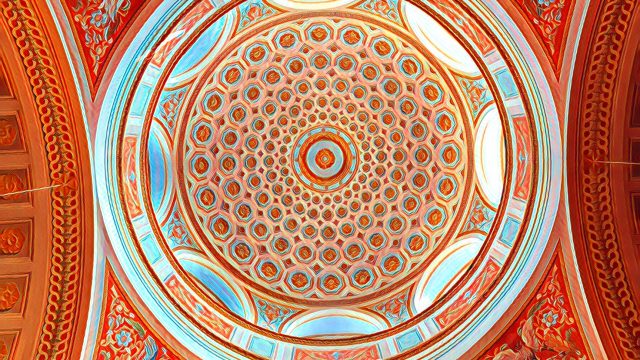こんにちは、映像翻訳者のル・モンです。
英語力を磨くためにC2レベルを目指しています。
C2レベルとは、言語における4技能(スピーキング・リスニング・リーディング・ライティング)を総合的に評価したレベル分けの最高峰です。
C2レベル=ネイティブレベル並みの英語運用能力を指します。


今回は「C2レベルのスキルが身についた状態=ゴール」をより具体的にイメージするためにC2レベルの英語学習において押さえるべきポイントを考えてみました。
・C2レベルって何?
・C2レベルの英語学習で押さえるべきポイントは?
・ネイティブレベルの語彙力はどれくらい?
・ネイティブレベルの読むスピードは?
・ネイティブレベルの頭の中はどうなってるの?
詳しく見ていきます。
C2レベルとは?

「C2レベル」は、CFER(セファール) という「ヨーロッパ言語共通参照枠」で測ることができる最上級レベルです。
CEFRはCommon European Framework of Reference for Languages の略。ヨーロッパを中心に活用されている語学レベルを共通の物差しで測る基準です。
日本でおなじみの英検もCEFRでのレベルを基準にスキルを比較できるようになっています。
リーディング、リスニング、スピーキング、ライティングの4技能すべてを評価対象としており、初級(A1,A2)、中級(B1, B2)、上級(C1, C2)の6段階でその言語のレベルが分かります。
「熟練した言語使用者」とみなされるC2レベル。
『見聞きしたほぼ全てを容易に理解。語彙力に優れ、根拠も論点も自分の言葉で自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。』とされています。

CEFRのレベル別できること
| C2 | 熟練言語使用者 | 読む、聞くほぼ全ての内容を容易に理解できる。口語・文語問わず、得た情報を要約し、根拠も論点も一貫した方法で再構築できる。自然に、流暢かつ正確に自己表現ができる。 |
|---|---|---|
| C1 | 熟練言語使用者 | 様々なジャンルで高度な内容のかなり長い文章を理解して、含意を把握できる。 言葉を探すために詰まることがなく、流暢に、また自然に自己表現ができる。言葉を柔軟かつ効果的に用いることができる。複雑な話題についても構成がしっかりした、明確で詳細な文章を作ることができる。 |
| B2 | 自立した 言語使用者 |
自分の専門分野の技術的な議論も含めて、抽象的・具体的な話題でも、複雑な文章の主要な内容を理解できる。母語話者とはお互いに緊張しないで普通にやり取りができるくらい流暢かつ自然である。幅広い話題について、明確で詳細な文章を作ることができる。 |
| B1 | 自立した 言語使用者 |
仕事、学校、娯楽などで起こる身近な話題について、標準的な話し方であれば、主要な点を理解できる。 その言語圏において、たいていの事態に対処することができる。身近な話題や個人的に関心のある話題について、筋の通った簡単な文章を作ることができる。 |
| A2 | 基礎段階の 言語使用者 |
ごく基本的な個人情報や家族情報、買い物、地元の地理、仕事など、直接的関係がある領域に関しては、文やよく使われる表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら、身近で日常の事柄について、単純で直接的な情報交換に応じることができる。 |
| A1 | 基礎段階の 言語使用者 |
よく使われる日常的表現と基本的な言い回しは理解し、用いることができる。自分や他人を紹介することができ、住んでいるところや、誰と知り合いであるか、持ち物などの個人的情報について、質問をしたり、答えたりすることができる。もし、相手がゆっくり、はっきりと話して、助けが得られるならば、簡単なやり取りをすること ができる。 |
参考:ブリティッシュ・カウンシル
複数の言語を使う人なら、例えば、「英語はC2レベルでドイツ語はB1レベル」とか、「スペイン語はA1で英語はB1」のように、自分のそれぞれの言語習得レベルを具体的に表現することができます。
英検1級を合格するレベルがだいたいC1レベルという目安もあるようですが、ギリギリ合格だとB2レベルに近いので、かなり幅があります。

独学で英語を上級レベルまで引き上げたい人は、最初から4技能を測り、スコアがそのままCEFRで把握できる試験を受けるといいと思います。
海外でも通用するCEFR評価が分かる試験は?
日本で人気のTOEICや英検でも、ある程度「比較」することで大体のレベルは分かると思います。(TOEICはS&Wを受ける前提で。)
でも、海外での就職や留学に必要とされる英語力を証明する、またはより高いレベルの英語力を試したいと考えている英語学習者には最初からCEFRを基準としている英語試験がおすすめです。
その点、IELTSは自分の現状レベルが把握しやすいのでおすすめです。
4技能すべての試験を受けて、トータルのスコアでそのまま自分がどのCEFRレベルに当てはまるのか分かります。
他にもケンブリッジ英検などもありますが、IELTSは試験開催が基本的に毎週あるので受験しやすいという利点があります。

IELTSスコア8.5到達するための試験対策として何をするか。
ほかの英語試験にも言えることですが、過去問を解くという正攻法をとる人が大半だと思います。私も例にもれずその1人です。
そして、勉強していくうちに自分の弱点を見つけたり、個別に強化していきたいポイントは出てくるものですよね。
ただ、闇雲に他の問題集を買い足したり、あれもこれもと色んな勉強法に手を出してしまって消化しきれず、目標を失ってしまっては元も子もないはずです。

C2レベルの英語学習で押さえるべきポイント3つ

英語でC2レベルに到達することは、ネイティブレベルの英語力を保持しているということ。
そのレベルに該当するケンブリッジ英検CPEと IELTSスコア8.5以上の各試験対策にも通じる、全体の英語学習ポイントを改めて考えてみました。
意識するべきポイントは3つあります。
〇 ネイティブ並みの語彙力を身につけること
〇 ネイティブ並みに読むスピードを速くすること
〇 ネイティブ並みの聴解力を鍛えること
巷には有料・無料ともに様々な教材が溢れています。
ネイティブレベルを目指すのであれば当然と言えば当然のことですが、非ネイティブがこの高いレベルに確実に到達するには、脱線しすぎたり、効果がないことに余計な時間をかけるのはナンセンスです。


「C2レベルの勉強に効果的なものだけ」を選び取るための押さえておくべき判断基準を意識しておくことで、目標がブレない効果があると思います。
どれくらいが「ネイティブレベル」?
例えば、読解を頑張って長文を読むことができても、C2レベルを目指すならその読む速さも意識する必要があります。
母国語ではきちんと自分の言葉で語ることができる内容なのに英語でどう表現するのか語彙を知らないばっかりに、たどたどしい印象になってしまうのも残念だと思うのです。

ここで先ほど書いた3つのポイントをより具体的に変換してみます。
〇 ネイティブ並みの語彙力を身につける ⇒ 3万語以上の語彙力を身につける
〇 ネイティブ並みに読むスピードを速くすること ⇒ 1分300語の速さで読解する
〇 ネイティブ並みの聴解力を鍛えること ⇒ リエゾン・イントネーションに慣れる
3万語以上の語彙力を身につける
英語をインプットする(聞く・読む)にもアウトプットする(話す・書く)にも、4技能すべてにおいて語彙力は重要なファクターです。
語彙力が高いほど理解力も表現力も比例して強化できます。
1分300語のスピードで読解する
文章を読むスピードが速ければ速いほど、多くの情報を取り入れることが可能です。
読み飛ばすだけでは意味がありませんが、ある程度スピードを意識することは、結果的に読解力を鍛えることにもつながります。
リエゾン・イントネーションに慣れる
母語の場合は、聞いたそばから内容を理解できると思います。
英語でも同様に聞こえた情報をその瞬間から理解できる聴解力を身につけることが大事です。
英語圏の英語だけではなく、世界で話されている様々な英語話者とのコミュニケーションをとる際にも有効です。
C2レベルを目指すためにNGな学習法とは
「語彙」、「読解スピード」、「聴解力」これらすべてを「ネイティブ並み」に高めてこそC2レベルの試験を突破できる。
簡単に言えば、これをそのレベルまで高められないようなコンテンツの教材は不要ということです。
C2レベルを目指すには効果が薄い「英語学習」(エンタメとしてならOK)
・ 面白そうだからといって(もちろん、気分転換にはOK)語彙レベルが低い書籍ばかり読んでいてもC2レベルまでの勉強にはなりません。
・ 単語帳を1冊だけ暗記しても、3000語しか掲載されていなければC2レベルを目指すには全然足りません。
・ リスニングにいいと言っても、映画やドラマを字幕つきばかりで見て内容を楽しむだけでは聴解力を鍛えることはできないのです。
C2レベルの勉強に意識するべき3つ「語彙」、「読解スピード」、「聴解力」をネイティブ並みにあげるとは具体的にどういうことなのか詳しく見ていきます。
ネイティブレベルの語彙数は3万語

Test Your Vocabularyという自分の語彙力を測れるツールのデータによると、ほとんどのネイティブスピーカーは2万から3万5000語を知っているとしています。
大卒などの学歴や年齢によっても差はあると思いますが、別のソースでは成人のネイティブの語彙力は4万とも5万とも言われています。
年齢別・ネイティブの語彙力
先ほどのサイトにはネイティブの語彙力を年齢別に表したグラフも掲載されています。

参考資料:Test Your Vocabulary
青いグラフが平均値になっています。
それによると、年齢別の語彙力はこんな感じです。
10歳 12,411語
20歳 23,078語
30歳 27,109語
40歳 30,086語
英検1級を受験する際の目安として、「1万語 ~ 1万5000語は覚えた方がいい」とよく耳にしますが、このグラフに当てはめると単純に言えば 9歳(10,306語)~ 13歳(15,228語)ぐらいの語彙レベルということになります。
大人のネイティブの語彙力
日本の成人が20歳なので、単純に20歳の語彙力=大人の語彙力として考えてみます。
20歳の平均語彙数は23,078語でしたが、同じ年齢の上位の数字は32,390語を示しています。
そして、グラフを見ると40歳以上は平均語彙数が3万語を超えてきています。
20歳以上の大人のネイティブと同じようなレベルで物事を知り、理解できるようになるには3万語以上あれば良いと言えそうです。
ツールで語彙力をチェック
先ほどのツールを使って、私の語彙力をチェックしてみました。

結果は20,600語だったので、16歳のネイティブの平均語彙数(20,548語) に近いです。
もう一つ、別の語彙数チェックツール Online English Vocabulary Size Testも使ってみます。このようなチェックツールは他にもたくさんあります。

結果は21,685語でしたので、先ほどのツールとあまり変わらない結果になりました。
コメントには 「専門的な事務職レベル」を意味する “at the level of professional white-collars in the US” と書いてありました。
ネイティブの語彙力が3万語以上だとすると、私がC2レベルのIELTSスコア8.5とケンブリッジ英検CPE合格するには、少なくてもあと1万語ほど覚える必要があると言えます。
母語の語彙力
Online English Vocabulary Size Testには他の言語の語彙力もチェックできます。
母国語である日本語の語彙力がどれくらいなのか、ついでに試してみました。
結果は…

日本語ネイティブだから3万語はいくのかの思えば、撃沈でした(笑)。学生時代は海外だったからとかいうどうでもいい言い訳はさておき… 後半の4字熟語や文学的な表現が難易度が高くてダメでした。
コメントには英語と同じ、「専門的な事務職レベル」を意味する “at the level of professional white-collars in the US”でした。
個人的には英語と日本語の語彙にあまり差がないのは好ましいのですが、C2レベルを目指すための英語語彙を底上げすると同時に、翻訳者としてもっと日本語も磨かなくてはと思いました。
語彙力を増やすには
数千~万単位の語彙数を増やすには、やっぱり「単語帳」を使って集中して覚える方が効果的です。
「ネイティブレベルの語彙数」をカバーするために普段の読書やネット閲覧で単語をピックアップして覚えるというやり方もあると思います。でもそれだけでは、時間がかかるうえに覚えた方がいい絶対数が足りなくなるリスクがあるのでコスパが悪いのです。
基本は単語帳をしっかり覚えてしまうことが得策です。
そう言っておいてなんですが、私は単語帳が苦手です。効率は良いのですが、読み物と違いどうしても飽きてしまうので、昔購入した単語帳も長く放置していた時期があります。
なるべく抵抗感なく単語を覚えるために、自分が楽しめる工夫をしています。
例えば、
〇 長時間、単語帳を眺めると飽きる → アプリを使いゲーム感覚で短時間で済ませる。
〇 毎日続かない → ワークブックタイプで1日1ページなどハードルを下げてルーティン化する。
〇 知らない単語ばかり続くと苦痛 → 覚えた単語帳を「読み物」として復習、解説にあ るような派生語などに目を通す。
〇 やっぱり単語帳を見たくない日 → 読み物として優れている「単語本」を読む。
無理なく単語を覚えるためには
語彙を覚えるためには、基本的になるべく沢山その単語を目にすることがおすすめです。
特に単語の勉強は、まとまった時間をとって暗記するというよりは、スキマ時間などを利用して小まめに覚えることができるので、自分の生活に組み込んでしまった方が効率的です。
もしある程度まとまった時間を単語だけに費やすことができるなら、寝る直前がおすすめです。
ある程度の数の単語を一気に読み込んでから寝てしまいます。
余裕があれば朝起きたときにもう一度同じ範囲を見て眺めると、結構定着しやすいと思います。

単語を暗記したあとの復習のタイミング
新しく覚えた単語の復習に関しては、有名な「エビングハウスの忘却曲線」を参考にできます。

参考資料:Intera
ちなみに上の参考資料にしたサイトでは、この忘却曲線には個人差があるということも伝えています。
ドイツの心理学者エビングハウスによって導き出されたこのグラフによると、人は物事を覚えた先から忘れていってしまうことが分かります。
単純に言えば、100個単語を覚えたとして、20分後には58個しか記憶に残らず、1日後にはさらに減って、33個しか覚えていられないということです。
単語は「忘れてしまうタイミング」に復習を行うと効果的。
例えば100個の単語を覚えたら、1時間後にまだ44個覚えているうちに忘れてしまった56個も含めて復習しておくと記憶が長持ちしやすいということになります。

「1日100個新しい単語を覚えて、昨日の100個を復習する」というやり方がいいというのは分かります。
でも、私は単語数を意識して繰り返すのが面倒なので、基本的には「1週間以内にまとめてもう一度復習する」方法をとっています。
グラフでいえば、1日後の33%も6日後の25%もそこまで大差を感じないのと、割とせっかちなので「なるべく一気にすすんで」から復習するイメージです。
早めのペースで何回もリピートするのもアリ。(個人差あり)
なんなら、単語帳1冊を1週間でサクサク読みきって、再び最初から読みなおすような、「早いスパンで何周も読む」方が自分には合っている気がします。
個人的には、やっぱり多読や多視聴など、単語帳以外でその単語に再び出会う、そして自分で実際に使うことで、自然に記憶に留めることができると思います。
おすすめの単語帳
〇 毎日のルーティン化に最適
1100 Words You Need to Know (Barron’s)
〇 読みものとして最適
Merriam-Webster‘s Vocabulary Builder (Merriam-Webster)
〇 基本の1冊として最適
英検1級でる順パス単 (旺文社)
〇 スキマ時間に最適
アプリ版・究極の英単語シリーズ (アルク)
そのほか、ボキャビルで実際に今まで使ってよかった単語帳と、その勉強法は別記事にまとめています。

単語レベルが分かるサイト
単語帳ではないのですがCEFR基準にそって押さえておくべき単語が分かりやすくリストになっている便利なサイトがあります。
Oxford University Press が提供している Oxford 3000 と Oxford 5000という単語リストがあります。
ネイティブレベルを目指すのであれば、Oxford 5000 に掲載されている単語を網羅すると良いと思います。
C2レベルとして紹介している単語は掲載されていませんが、単語ひとつずつがB2~C1レベルに分けられています。

ネイティブの読むスピードは1分で300ワード

読むスピードはWPM(words per minute)1分間で読める単語数で測ることができます。
Timothy Gutierrez氏(日本大学文理学部総合文化研究室の准教授)のある文献によれば、ネイティブスピーカーが娯楽のために読むスピードは1分間に300ワードを読むことができるとしています。
目的によってスピードは異なり、学習目的で読む場合は200wpmになったり、記憶する前提で読む場合は138wpmになるということです。
ほかのソースでも、ネイティブスピーカーの読むスピードは平均300wpmと記しています。
自分の読むスピードを測る
WPMを測るツールは色々ネットで探せますが、私は Speed Reading Test Online を使ってみました。

掲載されている文章をスタートボタン押してから読み始め、終わると同時にストップボタンを押すと自動でwpmを計算してくれます。
1回目:173 語/分

2回目:237語/分

同じ文章でも2回目の方が64語も多く読めました。
このサイトには、読むスピードの平均数値は200wpm(スクリーン上)で、内容の理解度は60%ということが書かれています。
読むスピードだけではなくきちんと理解しているかもテストできるようになっています。
その資料によると、スクリーンで300wpm、紙で400wpmの速さで読むことができ、内容を80%理解しているとgood readerのカテゴリーに入れるようです。
また、スクリーン上と紙上では、スクリーンの方が25%ほど読むのが遅くなるそうです。
読むスピードをあげるには
私のスピード結果でも分かりますが、2回目の方が初見よりも早く読むことができました。
先ほどの文献には、ノンネイティブの日本人が英語で書かれた文章を5回繰り返し読んだ結果、ほとんどの対象者が大体40wpmほどスピードがあがったとしています。
同じ文章なら繰り返し読むことで、自然に早く読めるようになるということです。
個人的には、同じ文章ではなくても、似た内容や難易度の文章をたくさん読むことによって全体的な読むスピードは上がると思います。
要は多読です。色々な語彙や文法に文章でたくさん触れることによって、読むリズムや知識も増え、結果、文章全体を読むスピードは速めることができると思います。
多読用におすすめの本
ここでは、中級以上の英語レベルがあれば比較的読みやすく、時事ネタの背景知識としても役に立つと思う1冊をご紹介します。
『Numbers Don’t Lie: 71 Things You Need to Know About the World』
 画像:Amazon
画像:Amazon
Valcav Smil(バーツラル・シュミル著)
「国」「人」「食」「環境」「エネルギー」「移動」「機械」という7ジャンルから71のトピックについてとりあげ、グローバル時代における世界の現状を数字を用いて把握できる1冊なので、ビジネスパーソンの教養本としても役に立つかと思います。
『Number’s Don’t Lie 世界のリアルは「数字」でつかめ!』のタイトルで翻訳版も出ていますが、英語学習者には是非、英語でトライすることをおススメします。
Numbers Don’t Lie おすすめポイント
① 字が大きめ
② 1トピックが3~5ページくらい
③ グラフや表が多い
ペーパーバックでも、字が大きめな本なので340ページ強の本ですが比較的スムーズに読み進めることができると思います。

グラフや表なども多く使われていて視覚的にも分かりやすいですし、情報を数字ベースで比較でき、論理的に考えることができます。
そして、個人的には1トピックが3~5ページなので読みきりやすいところもポイントが高いです。

どのトピックから読んでもいいので、私はまず目次を読んで「日本」がトピックにあがっている章から先に読んだりしました。
IELTSのライティング試験など、CEFRを測ることができる4技能試験にはグラフや表から読み解く記述問題のようなものもあります。このような本を読んでいれば抵抗なく受験できるのではないでしょうか?
おススメ単語本としても既出ですが、『Merriam-Webster‘s Vocabulary Builder』も多読用の1冊としておすすめです↓

注意!読むスピードが速い=読解力が高いとは限らない
ここで気をつけなければいけないのが、読むスピードが速くなったからといって読解力が高くなるのかというとそうではないということです。
私は自分の英語を読むスピードはネイティブに比べたらまだまだ遅いですが、割と一般的な速さだと感じています。
例えば、IELTSの公式問題集のリーディングセクションは60分で40問解く必要があります。
私の場合、40~42分くらいで解きます。
ただし、正答率が高いかというとそうでもありません。
8.5以上を目指すには全問正解しておかないと厳しい。
リーディングでは、40問中全問正解、もしくは39問正解しておかないとC2レベルは厳しくなります。
私のスピードは試験問題を解くペースとしてはOKですが、正解数が30~35前後なので、その時の回によっても想定スコアは大幅に変わってきます。

解いている時はこれが正解だと踏んでるのですが、結果、間違っているので解釈が怪しい個所があるということですね。
読解力は全体を正しく要約できるかどうか。大切な情報をきちんと処理できるかどうかが大切です。
文章中の大事なキーワードをピックアップして頭の中で要約するトレーニングも多読で読むスピードをあげ、その速さを維持しながら行うとより効果的な試験対策になると思います。

ネイティブレベルの頭の中には英語を自動的に処理する回路がある

私は母語の日本語を聞いたそばから理解できます。
もちろん、かなり専門的で自分には不可解な内容は除きますが、大抵のことは音を聞いた時から時差がなく内容を理解できると思っています。
これは、私が「日本語脳」を持っているからです。日本語の単語を知っていて、それがどう発音されるかも分かり、日本語の文法でどう組み立てられて意味をなしているか、を理解できる言語処理の回路を持っているというイメージです。

当然ですが、英語ネイティブには同じように英語の回路あります。
日英バイリンガルには日本語の回路と英語の回路が頭の中にある。
この回路強化を意識することで聴解力も鍛えることができるはずです。
聴解力を鍛えるには
ネイティブレベルを目指すなら、「聞いたそばから内容を理解できるよう」にこの回路を強化する必要があります。
言語習得の臨界点を意識すると、英語ネイティブとして育つには10歳ぐらいまで英語圏で生活していた方がいいとは思います。
でも、単語をスペルだけではなく正しい発音と一緒に覚え、なおかつ、それがどのように会話で使われているかを意識することで、ノンネイティブでもいわゆる英語脳の回路は強化できると思います。
生活の中での英語リスニング比率をあげて聴解力を鍛える。
もちろん、脳の回路に必要な「文法」や「語彙」という要素も一緒に高める必要はあります。
おすすめは、BBCやCNN、ABCなどの海外ニュースやTED、好きな海外ドラマなどを字幕なしで視聴することです。
私は映像翻訳者なので、日英も英日も勉強や表現のリサーチの一環で字幕つきで見ることもあります。
でも、娯楽で見る範囲ではなるべく字幕なしで見るようにしています。字幕があることで、内容を理解して楽しむことはできると思うのですが、それに頼ってしまって英語をたくさん聞いているはずなのに、実はあまり英語力が伸びていなかったという状況になるリスクがあると思うのです。

C2レベルを目指すなら、自分の英語脳を鍛えるどんな機会も逃さずに、娯楽タイムでもちゃっかり聴解力トレーニングしてしまったほうがお得で効率的です。
聴解力を鍛える時はナチュラルスピードで
英語力を強化するメソッドとして、シャドーイングというものがあります。
これは聞こえた英語音声をそのまま復唱することで、発音も整え、リスニング強化になる勉強法で、慣れないうちは聞き取れるスピードの音声を使うことが推奨されます。
ただ、「聴解力」を鍛えるには、シャドーイングで自分のレベルに合わせたスピードの音声を選ぶというものとは別で、最初からナチュラルスピードで鍛えるということが効果的だと思っています。
実際にネイティブが使っている速さに慣れ、それを理解することをしていかないと、C2レベルもそうですが、何より実生活であまり実践的ではないからです。
字幕なしで英語番組を視聴する
ナチュラルスピードの英語に慣れるには、英語のラジオやポッドキャスト、オーディオブックを聴くこともおすすめです。
ニュースやリアリティ番組のような、普段の会話を聞くことができる番組やYouTube動画もおススメです。
字幕なしで色々な番組を視聴するメリット
〇 ネイティブ特有のリエゾンや子音の聞き分けに慣れることができる。
〇 色々なスピーカーに慣れておくことで訛りや方言にも慣れる。
リアルな英語話者のイントネーションにも注目
英語を話すノンネイティブは多いです。
グローバル化が進んだことで、英語圏だけの英語というよりも、それこそノンネイティブの英語話者ともコミュニケーションをとる機会も増えています。
英語と米語にあるように、使われている単語や表現がまったく違うケースは知識をつけるしかないですが、イントネーションや発音に関しては個人差はあるものの、慣れることで聞き分けることができるようになります。

私の英語力ではまったく分からなかった「ノンネイティブの英語スピーカーの話」を、知人の英語ネイティブの日本人が理解して驚いたことがあります。
本人に聞くと、何となく言葉の雰囲気で想像はついたのでコミュニケーションがとれたとのことでした。

例えば、あまり日本語が得意ではない海外の人に話しかけられた場合の私の聴解力はどうなのか考えたら、やっぱり、なんとなくでも相手の言っていることは理解できるのではないかと思います。
自分の母語である日本語だと、日本語脳の回路がピピっと働いて、上手いこと情報をまとめてくれるような気がします。
相手の話を理解しようと意識をして、自分の言語回路をフル稼働するイメージです。
頭の中の英語回路をネイティブレベルにするべく、聴解力を鍛えると、これと同じようなことができるようになると思います。
聴くだけでなく話してみよう
様々なソースで聴解力を鍛えると同時に、相手と会話してみることも大切です。
インプットとアウトプットをバランスよく行った方が英語スキルは伸びると思うからです。
会話するメリット
会話のキャッチボールをすると、自分がきちんと理解できているのか、リアクションの間は自然なのかが把握できる。
ネイティブと話すことで、相手の話した内容が理解できなかったら微妙な回答になりますよね。

リスニングとスピーキングは、赤ちゃんから徐々に言葉を覚える時に身につけるスキルです。聴解力がついてきた感じたら、是非、スピーキングも試してみるといいと思います。
おすすめのオンライン英会話
ネイティブが周りにいない、話す機会がない、間違えたら恥ずかしいなど、会話の相手に困ったらオンライン英会話がおすすめです。
今の時代、どこにいようがネイティブと気軽に英会話を楽しむことができます。
私が使っているおススメの英会話は Cambly (キャンブリー) です。予約なしでも、空いた時間にすぐ会話できる&英語圏ネイティブの色々なアクセントに触れることができます。
自分は発音、イントネーション、アクセントが苦手?それとも文法や語彙が足りない?など、とにかく話してみないと、具体的にどこが弱いのか分からないということもあると思います。
数あるオンライン英会話の中でも、英語レベル関係なくおススメです!
まずはトライアルで15分くらい、実際に会話してみると自分の英語コミュニケーションのクセも分かるのでいいと思いますよ。

おすすめの英語コーチング
本格的に「話せる自分」にバージョンアップしたいなら、やはり避けて通れないのが「発音」と「流暢さ」です。
英語コミュニケーションにおいて、「聴解力」にも「発話」にも関係してきます。
3か月の短期集中する覚悟で、自分の時間とお金を投資することができるなら、スピーキング能力を引き上げる「英語コーチングスクール」がおすすめです。
なかでも、”本当に話せる英語力の証明” VERSANTテストでの「発音」と「流暢さ」スコア向上の「伸び」実績がスゴイ、The Past (ザ・パスト)の VERSANT対策プログラムは、ネイティブの発音に近づくためのスキルが体系的に身につけることができます。
外国人講師による発音矯正含む『実践型トレーニング』と、言語学習得のプロである日本人コーチによるフィードバックや学習計画などの『理論的サポート』。


独学ではなかなか難しい、発音と流暢さを鍛えることができます。

The Past (ザ・パスト)のVERSANT対策プログラムについてはこちらの記事にも詳しく書いています。

3つのポイントおさらい

「C2レベル」というネイティブレベルの目指す英語学習で押さえるべきポイント3つとは…
〇 語彙は3万語以上を目安に身につける。
〇 多読で読むスピードを300wpm近くまであげる。
〇 海外ニュースやドラマを字幕なしで聴解力を鍛える。
C2レベルのIELTSスコア8.5やケンブリッジ英検CPEの試験対策として、公式問題集で出題傾向や時間配分を知ることは必須ですよね。
語彙、文法、スピーキング、リスニングなど、自分が強化したいエリアを個別で対策をとる時は「具体的にどれくらい?」を意識することが大事です。
漠然と「この単語帳を1冊覚える」ではなく「トータルで3万語以上」を目安に、「毎日、海外ドラマを見る」ではなく、「字幕なしで理解する」のようなイメージです。
以上、C2レベルを目指すうえで意識するべき「語彙」「読解スピード」「聴解力」をそれぞれ具体的な数値や目安を取り入れて考えてみました。