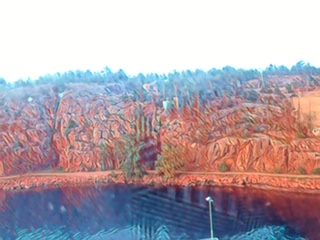この英語の対訳、日本のメディアはなんて表現してたっけ?
こんにちは、映像翻訳者のル・モンです。社内翻訳者としても働いています。
社内翻訳者として働いていて、翻訳表現について確認したいとか、少し自信がないところを誰かに相談したい、と思ったことはありませんか?
翻訳や英語の観点で相談できる仲間や上司がすぐ近くにいたらいいですが、職場で翻訳関連の仕事をしているのが自分ひとりしかいない場合もあると思います。
そして、別に翻訳者として働いているわけではないのに、一番英語ができるのが自分だからってなんでも英語関連の仕事が回ってくるという場合も。
そういう時は自分の判断があっているのか、ちょっと心細くなりますよね。
私の場合、映像翻訳という専門スキルはあったものの、実務的な翻訳はほぼ実戦で覚えたようなものです。
そこで今回は、私が背伸びして頑張っていた駆け出し翻訳者のころに持っていてとても役に立った本を紹介したいと思います。今でも、改めて読み直して使える!と思うほど重宝している本です。

駆け出し実務翻訳者の強い味方!持っていれば安心のおすすめ3冊
駆け出しの翻訳者におすすめの本をタイプ別で3冊選んでみました。
細かい表現などの参考にほかにも色々おすすめの本はあるのですが、今回は「持っていたらいざという時に安心する」という視点でピックしています。
自分にあてはまるタイプを参考にしてみてください。
タイプ①:社内翻訳として働くのに特に不安はない

こちらのタイプは、英語力や翻訳経験もあり既に自分の得意不得意も分かっている、または必要なツールや困ったときにはこうする、という何らかのメソッドをお持ちの翻訳者さんだと思います。
もしくは、これから新しく英語関連の仕事として社内翻訳を始めようとしているかたで、経験が少ないから「自分が何に困るかも正直、ちょっと漠然とし過ぎて分からない」というビギナーの方も含めてもいいかもしれません。
このような方におすすめなのはこちら。
ジャンル別 トレンド 日米表現辞典 (小学館)です。

政治・経済・医療・情報・環境など、31ジャンル1万8000項目の「現代用語」が日本語と英語で表記してあります。
この本の使い方
例えば、自分の働いている企業の業務体制が変わって新しい部署ができたとします。
社内の各部署を英語名にするということで、部署名に適した英訳を考えることになった場合、ほかの企業が似たような業務の部署名をどう英語で表現しているかなどもリサーチする必要があります。
そんな時は、「企業組織・部署名の実例」というページを開き参考にできます。
組織や部署を表現するにも、division, unit, department, group, laboratoryなど色々あるので、自分が訳そうとしているものに対して適切な表現はどれか、調べて比較するのにとても便利です。
この本のメリット
調べたい事柄がジャンル別に分かれているので探しやすいと思います。
先ほどの「部署」に対する英訳を考える時、最初からネットで調べるのは結構時間がかかるものです。実践的な例がまとまっているので時間節約につながります。
読み物として、一度通読してみるのも面白いと思います。政治や医療など、普段見聞きするニュースに使われている語彙が多いのでボキャビルにもなり、英語力アップにつながります。
ある大手の通訳学校ではこの本を丸暗記するように課題が出るらしいです。
通訳は、その場ですぐに適した表現をアウトプットする必要があるため、確かに暗記してしまった方がいいというのは納得です。
「文部科学省」や「日米安保条約」など、受注した仕事によってどんな語彙が必要になるかは全然違うものですから。
個人的に、オフィスに1冊あるといざという時に便利な本だと思います。
また、多ジャンルの翻訳を短時間で行う必要がある職場にいるような人にも、お守り感覚で身近に置いておくと、判断に迷ったときに頼りになる1冊としておすすめです。
この本のデメリット
「トレンド」という名の辞典ではあるものの、今のところ2007年に発売された第4版が最新となっています。
個人的にはそれでも十分、参考にしているのですが、中には少し古く感じる情報もあります。
「情報・通信」のジャンルにあるメールなどで使う略語も、既に使わないものも含まれている気がします。もう少しアップデートした「改訂版」が出るといいなと思います。
辞典とは言え、中には誤植のような個所も見受けられるようです。(ほかのレビューで指摘されているのを読んだことがあります。)
翻訳に生かすのであれば、そのままコピペのように使うのではなく表現を参考にしたうえで自分でも再度ダブルチェックすることが大切だと思います。
値段は3080円です。これを高いと感じるか、安いと感じるかは個人差があると思います。
「企業やメディアの名前や事業が出てくるCSRやPR系の英訳・和訳が多い」人や、「ボキャビルの一環でニュースに使われているような実践的な英語表現を知りたい」人にはおすすめですが、英語関連の仕事といってもそこまで難易度も高くないし、頻繁に発生しない職場で働いている翻訳者には向いていないかもしれません。
タイプ②:英語は理解できるのに、こなれた日本語表現がイマイチ

英語の解釈はできるのに、それをアプトプットする時にどうしても原文に引きずられて少し不自然さが残る日本語になってしまう経験ありませんか?
私は映像翻訳を日英メインで受注していた関係で、英日翻訳を頻繁に行うようになったのは実は社内翻訳を並行して始めてからでした。
カジュアルなものから、かたい内容のものまで色々と翻訳するようになり、母国語とはいえ、日本語表現にとても敏感になったのです。
そこで参考として手に取った本がこちらです。
英文翻訳術 (ちくま学芸文庫)
 画像:Amazon
画像:Amazon
翻訳学習者の中では割と有名な一冊です。熟練翻訳家の著者が翻訳実例なども交えつつ、翻訳の技術に特化した専門書。
母国語だから伝わるだろうとこねくり回した結果、原文の意味を損なってしまったり、伝わらない文章になって失敗するということはこの本を参考にしたら避けられると思います。
この本の使い方
読み物として1度は通読することがおすすめです。それだけでも、自分が普段やっている英日翻訳の組み立て方などと比較して参考になります。
2度目以降は、実際に自分でも翻訳してみてそれを基に読み進めることも勉強になるのでおすすめです。自分の翻訳のクセが客観的に分かります。
この本のメリット
著者は権威ある翻訳家の安西徹雄氏。その翻訳メソッドを体系的に実例も合わせて学ぶことができます。
「原文の文法にそって抽出した要素」と「文脈から表現したい要素」などをどういうバランス(順番)で組み立てるといいのか、英日翻訳のヒントがたくさん載っている本です。
英文を正しく解釈したけど、その要素を全部入れようとした結果、日本語がイマイチになってしまう。私はこういうところに良くつまずいていたけれど、なんでそうなってしまうのか原因が分かるようになり英日翻訳の質もあがったと感じています。
この本のデメリット
個人的には翻訳に携わる多くの人におすすめの1冊です。
でも「英語ができるから翻訳をしている」人の中には、それほどの翻訳スキルも文法力もないまま、仕事をしている人もいるのかもしれません。
なんとなく分かる範囲で上部のニュアンスだけをくみ取ってしまい、「こんな感じの内容です」とアウトプットするような仕事をする人には向かない本だと思います。
まずは文法の細かいニュアンスまで分かろうとすることと、原語の意図をきちんと伝えたいという気持ちがない人には、もはやこの手のメソッド本は必要ないですね。
AはBのように訳すというような、答えがのっているhow to 本みたいなものを探している方には不向きです。
タイプ③:英訳することが多い&自分の英語解釈に不安がある時がある

「これ、英訳しておいて」「海外にメールしておいて」など、日本語を英語に翻訳することが多くなった社内翻訳者もいるのではないでしょうか?英日よりも日英翻訳の方が比率が多いということもあると思います。
そして、英語は得意で、翻訳の経験も長くなってきたとしても、やっぱり「あれ、これってどういう意味になるんだっけ?」という状況になることも出てくると思います。
単語などは覚えていても、スペルは漢字と同じくらいしょっちゅう忘れてしまいます。
文法にも同じことが起こります。
長文で複雑な文章を翻訳するときに、今一度、解釈を間違えないためにも文法書で調べなおす癖がついています。
使いやすい文法書は人によって違うと思いますが、私のお気に入りの1冊はこちらです。
表現のための実践ロイヤル英文法 (旺文社)

ほかの記事にも書いていますが、これと並行して私は上級レベルの文法書や英語圏で使われている文法書やスタイルガイドなども使っています。でも、基本の1冊としてはこのロイヤルをおすすめしています。
この本の使い方
分からない文法項目にぶつかったときに、その都度、辞書のように使って調べるというのが基本になると思います。
でも、少し分厚さもありますが、一度は読み物として通読することを強くおすすめします。
私は、個人的に文法のジャンル名が苦手です。海外で学生生活を過ごしたというのもありますが、英語をそこまで細かい「用法名」で身につけては来なかったので。
英語の先生をしている方であれば、文章をみて、すぐにこれは「条件節と帰結節の時制」の項目をチェックすればいい、とかどのページを開けば答えがのっているのか探しやすいと思いますが… (そんな単語がすぐ出てくる方は文法完璧な気もしますけど(笑))
一度通読しておいて、自分が少し苦手かもしれない、とか、理解しているけど怪しいと感じている項目が「どういう文法名で、どの個所に記載されているのか」に目安をつけておくだけでも、自分にとって使いやすいツールになります。
この本のメリット
基本的な文法を、シンプルに解説しています。本のタイトルに「表現のための」とあるように、とにかく英語的に自然な例文がふんだんに掲載されています。
文体、口語体あわせてナチュラルな英語フレーズが多く、音読してみて覚えてしまえば英語の会話やライティングなど、自分のアウトプット力も同時に磨くことができます。
付属品として300フレーズの音声CDがついているので、その代表的な文法要素を入れ込んだフレーズは暗記するのがおすすめです。実はとっても役に立っている優れものなんです。
この本のデメリット
難易度が高いというわけではないのですが、ほかの文法書に比べたら絵や図解はありません。
例えばよくある、in, on, overなどの前置詞の違いなどを図解で説明している文法書は多くありますが、この本はそういった文法の概念のところから学ぶというよりも、本当に「表現」に焦点をあてています。
だからこそ、翻訳者など文章を書くにあたって、ある文法が実際に文章にするときにどう表現するのかを確認できる実践的な本といえます。
そのため、文法要素の概念から細かく知りたい人の基本の1冊には向かないと思います。
まとめ

社内翻訳と一言でいっても、仕事内容は働く会社によってもいろいろ違うものです。
翻訳専門の部署で働くというだけでなく、中には一般社内業務もこなす必要がある職務から、たまに発生する「英語関連の仕事のみ」という場合もあると思います。
翻訳案件の規模も頻度もケースバイケース。
自分が専門と考えていなくても、社内で翻訳をする、または英語関連の仕事を探してたどり着いたポストにはいつどんな英語案件が飛び込んでくるか分からないのも事実です。
そんな時、自信がないからといって「できない」と断ってしまうのはもったいないですよね。
もちろん、専門やスキルを度外視したレベルは逆に迷惑をかけてしまうリスクが高ければ、前向きな提案と一緒に断るということも社内翻訳者には必須スキルだと思います。
でも、特に駆け出しのころはどんな案件でもチャレンジするという姿勢が大事です。
周りに英語や翻訳関連の質問ができる人がいない時はなおさらお守り感覚で持っていると安心できる3冊をタイプ別にご紹介しました。
「社内翻訳として働くのに特に不安はない」タイプ → トレンド日米表現辞典
「英語は理解できるのに、こなれた日本語表現がイマイチ」タイプ →英文翻訳術
「英訳することが多い&英語解釈に不安がある時がある」タイプ → 表現のためのロイヤル英文法
私は映像翻訳(字幕やその他メディア資料翻訳)だけではなく、契約書や指示書、企画書や議事録、プレゼン資料、ホームページやフォーマルレターなど、トーンもテイストも異なる文章の日英、英日翻訳に幅広く携わります。内容だって様々です。英語関連のコンテンツを作るプロジェクトにも参加しています。
ネットでも無料で簡単に調べることもできる時代ですが、書籍には情報が体系立てて書かれているので分かりやすいです。
何より、きちんと根拠になる情報は判断の基準をクリアにしてくれるので、結果、自分の自信につながると思います。長い目で見たら有益な投資ですね。