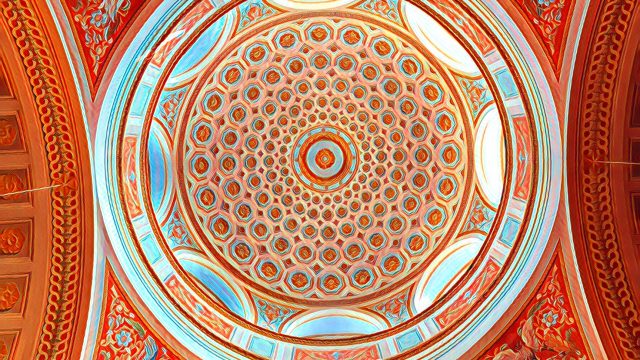こんにちは、映像翻訳者のル・モンです。
毎年、年末年始になると、「今年はこの目標を掲げていたのに、上手くできていないな」とか、「割と続いていたのに、いつから手を付けていないんだろう?」と、感じることがあります。
今回はあらためて、物事の習慣化について考えてみました。
継続できる人が一番つよい理由

継続できる人は何かしら「成し遂げている」人だと思うのです。
野球のイチロー選手も、長年テレビに出演し続けている芸人さんたちも、ジャンルや業界は違っても第一線で名を上げている人たちはみんな、常に努力をして、適応し、進化していると思います。
「一流」と呼ばれる人たちの中には、努力を努力とも感じていない、ただの習慣としてとらえている人も多いらしいです。
無意識に努力して質を高め、価値を生み出しつづけることができる人というのは、シンプルにビジネスでもなんでも、どんな状況においても最強だと感じます。
1万時間の法則
マルコム・グラッドウェルのベストセラー”Outliers”に出てくる、「1万時間の法則」は有名ですよね。
その道の一流になるには、スキルや学習に1万時間を費やす必要があると説いたものです。
確かに世界的に活躍する音楽家やスポーツでオリンピックにいけるような10代のスター選手たちは幼少期から習い始め、練習を毎日続けている人たちですよね。
この法則がどのジャンルにも当てはまるかというと、そうではないように思いますが、「質」をあげるには大量の「練習時間」をこなす必要がある、ということは分かります。
ある物事を長い期間、継続できる人はそれだけで、実行力も強いし、メンタル(これだけの量をこなしてきた、という自信もある)も強いと思います。
キャリアの大三角形
藤原和博氏が推奨している「キャリアを3つ掛け合わせて100万分の1の人材になる」というものにも、「継続は力なり」の要素が入っています。
ひとつの分野で5~10年かけてスキルを習得し、その3つを掛け合わせると人材としての「レアキャラ」になるということです。
ある分野で、1位になるということは相当難しいですよね。有能なスポーツ選手でも、1つのことに打ち込んで、世界1位を目指していたのに途中、怪我で断念せざるを得ない状況になることもあります。
その分野で1位にならなくても、1分野で自分のスキルを100人に1人くらいまでもっていき、それを3分野で1/100 x 1/100 x 1/100 = 1/100万 の希少性を得るという考え方は多様な個性を反映し、これからの時代にマッチしていて、強いのではないかと思います。
勉強を習慣化するコツ:社会人

1分野に5~10年を費やそうと考えた場合、普段の仕事で携わる分野なら勤続年数と比例してスキルを磨く時間は増えていきます。
でも、ほかの分野の知識を同時に深めたい場合は本業の負担にならない程度に上手く日常に組み込んでしまった方が得策です。
特に勉強が続かない人におすすめなのは、朝の時間を制することです。
人によって、朝方夜型など勉強に集中できる時間帯は違うと思うのですが、まずは「習慣化するための一歩」として「寝起きすぐ」がベストです。
目覚めてすぐ横になったままでOK
「朝活しよう!」と意気込んでいても、冬の寒い日にベッドから抜け出せず、気づいたら時間が無くなっていた。。。という失敗を繰り返さないためにも、横になったまま始めることが自分の経験上、ベストでした(笑)
ポイントは「寝起き直ぐ」と「音読」です。
寝起きだと、色んな雑念が生まれる前に着手できます。
音読して声を出すことで目が覚めます。
読みたい本、テキストなどは枕元に置いておき、目覚ましのアラームと同時に手を伸ばし、開いて声に出して読み始めてしまいましょう。
目が疲れているなら耳を使う
夜遅くまで読書やスマホを使っていて、目覚めても、字を読む気分ではない朝もあると思います。
そんな時は「音声」で学習することがおすすめです。
私は、もっぱらこっち派です。寝起きに英語ラジオのシャドーイングをするのですが、目をつむったままでもできるので、頑張らないでもできてしまいます。(翻訳の仕事をしているので、毎朝、英語でニュース情報を得ることを自分に課しています。)
あくまでも、「声を出す」ことは必須です。でないと、二度寝することになります。
資格試験などのテキストを覚えたい時は、事前準備として自分の声で音読したものを聞きながらシャドーイングするスタイルでも良いと思います。
読んで(目と口)音を聞きながら(耳)シャドーイングする(口)ことで、暗記力もアップします。
シャドーイングのやり方はこちらでチェックできます↓


勉強を習慣化するコツ:アプリ

忙しい社会人なら、スキマ時間をいかに「無駄なく」使うかがポイントになります。
そして、それを可能にしてくれるのが学習系アプリです。
タイムロスを防ぎ、すぐに勉強できる環境を整えるという意味でも是非、相性のいいアプリを携帯にインストールしておくことをおすすめします。
普段の生活で「時間がない」から継続できない、習慣化することができないと感じている人には、アプリを有効活用することで勉強が無理なく習慣化できると思います。
アプリを使うタイミングを決める
アプリはインストールしているけど、入れっぱなしだという人や、学習系アプリを使っているけどそこまで上達した気がしないという人は、アプリを開くタイミングを決めるといいと思います。
「勉強しているつもり」だったけど、実はアプリを使って学習するスピードと回数が足りていないという可能性があります。
それを克服して、自分のスキルアップのための有益な習慣化をアプリで身につけるために、まず、やっておくべきことがあります。
① 不要なアプリはスクリーンから省く。
② スキマ時間を把握する。
まずは、すぐに目がいく携帯のディスプレイには自分の選抜メンバーで優先順位が高いアプリのみにし、不要なものは削除するか、下層のページに移動させましょう。
そして、自分の1日の生活でどれくらい「スキマ時間」というものがあるか、1度、測ってみるといいと思います。
通勤途中、ホームで電車を待っている時間、食事前後のちょっとした時間、寝る直前、入浴中など5分~15分くらいの細切れ時間が結構見つかると思います。
例えば「食後のこの時間は必ずこのアプリを使う」のように決めてしまうと、その行為をする時がアラーム代わりになり、アプリを開くタイミングが習慣になります。
スキマ時間活用法&スキマ時間を把握する簡単な方法はこちら。

英語学習におすすめのアプリ
言語学習とアプリはとても相性がいいと思います。
4技能(聞く・話す・読む・書く)を身につけるために最近は質の高いアプリが豊富なので、多読多視聴、資格試験、発音強化、語彙強化など目的別でアプリをセレクトできます。
言語習得のための学習や知識を深めるための読書・ニュース視聴などは質の高いアプリが色々出ているので自分にあったものをすぐ開けるようにスマホなどの最初のスクリーンに設置しておくといいでしょう。
英語学習におすすめのアプリはこちら。



勉強を習慣化するコツ:期間

人が新しい習慣を身につけるために必要な期間は、18日~254日だそうです。個人差があるので、早ければ約3週間、長くて約9か月ということです。
月に数回、週に1回などで集中して勉強するより、少しずつでもスキマ時間を使って「小まめにたくさん」学習し、習慣を味方にしたほうが、知識の蓄積も早いと思います。
特に、記憶を維持するという意味でも、短期間に繰り返し復習するということは有効だと言われています。少しずつでも毎日、回数を増やすことで、改めて時間を作りがっつりと復習せずとも、そのまま記憶に定着しやすいと思います。
消費者としてモノやサービスを買う時も、費用対効果を考えますよね。新しいものや、良いと思うものはあれこれ試したくなるものです。
でも、結果的に身の回りに残るのは、自分の生活に「無理なく馴染んだもの」だけのことも多いと思います。
習慣化するコツは、「自分が長く使っている姿が想像できるかどうか」も大事なポイントです。
まとめ:無理なく継続できる力を手に入れる

「継続すること」がいいことだと頭でわかっていても、上手くいかないこともありますよね。
私は「年明けの抱負」を立てても(どうせ)挫折してしまうことが多いので、1年を通して割と小まめに目標を掲げるようにしています。
無意識に始められる環境を整えることで(アプリをセット、勉強する内容を決めておく、デスク回りに本を開いておくなど)タイムロスを防ぐことができます。
無意識に始められる時間を有効活用する。(寝起き一番はあれこれ考えこまず、体で覚えてしまういいタイミングだし、日常のフローにそったスキマ時間にやることを決めてしまうとアラーム代わりになる)やらない・できない言い訳を考える前に、「とりあえず」さっとできるよう自分を持っていくと上手く行きます。
私は、SNSを何となく開く前には必ずこのアプリを開いて1レッスンまたは1記事読んでから、というようなルールも数週間続けていくうちに「無意識に」できるようになりました。